目次
戸籍謄本等の請求
職務上請求を理解するには前提として、原則的な戸籍謄本等の請求について理解する必要がある。そこで、はじめに原則的な戸籍謄本等の請求について説明する。戸籍謄本等の請求には本人等請求と第三者請求がある。
戸籍謄本等の本人等請求
戸籍法10条1項は、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下、「戸籍謄本等」という。)の本人等請求について規定している。
また、戸籍謄本等の本人等請求における「本人等」とは次の者である。
- 戸籍に記載されている者
- 戸籍に記載されている者の配偶者
- 戸籍に記載されている者の直系尊属
- 戸籍に記載されている者の直系卑属
以上が「本人等」にあたる者である。戸籍謄本等の情報は重要な個人情報であるので、戸籍謄本等を請求できる者は限られている。また、本人等が請求できる戸籍謄本等の範囲は次のとおりである。
- 戸籍に記載されている者の戸籍謄本
- 戸籍に記載されている者の戸籍抄本
- 戸籍に記載されている者の戸籍に記載した事項に関する証明書
以上が本人等が請求できる戸籍謄本等の範囲である。
なお、除籍された者も除籍された戸籍謄本等を請求できる。例えば、婚姻により自分の親の戸籍から除籍され、配偶者の戸籍に入籍した者は婚姻前の自分の戸籍、すなわち自分が除籍された旨の記載のある親の戸籍謄本を請求できる。
戸籍謄本等の第三者請求
戸籍法10条の2第1項は本人等以外の者の戸籍謄本等の請求について規定している。この請求は戸籍謄本等の第三者請求と呼ばれる。戸籍謄本等の第三者請求における「第三者」とは次の場合に該当する者である。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
戸籍謄本等の第三者請求はこのような場合に請求できるが、3の場合は1及び2の場合より抽象的・概括的に表現されている。しかし、3の存在によって1、2以外の場合が広く認められるという趣旨ではない。すなわち、3の「正当な理由」は、1、2に準ずるものでなければならない。
そして、第三者がこれらのいずれかに該当する場合、戸籍謄本等の請求書にはその該当する理由を記入する。具体的には上記1、2及び3の場合に応じて次の理由を記入する。
- 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
- 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
- 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
なお、この3つの理由は司法書士の職務上請求書1号様式の「利用目的の種別」の2欄の「依頼者について該当する事由」と同じである。
また、戸籍謄本等の第三者請求においては、請求する戸籍謄本等の範囲について戸籍謄本等の本人等請求のような制限はない。すなわち、戸籍謄本等の第三者請求の対象は請求者本人、その配偶者、直系尊属及び直系卑属の戸籍謄本等に限られない。
以上が戸籍謄本等の請求である。また、本人等請求及び第三者請求いずれの場合でも、委任状を添付すれば任意代理人も戸籍謄本等の請求ができる(戸籍法10条の3第2項)。つまり、司法書士はこの委任状を添付して本人等請求又は第三者請求をすることで職務上請求で取得可能な戸籍謄本等と同じ範囲の戸籍謄本等を取得できる。
住民票の写し等の請求
次に原則的な住民票の写し等の請求について説明する。住民票の写し等の請求には本人等請求と第三者請求がある。
住民票の写し等の本人等請求
住民基本台帳法12条1項は、住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下、「住民票の写し等」という。)の本人等請求について規定している。すなわち、市町村が備える住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に属する者の住民票の写し等を請求できる。
以上が本人等が請求できる住民票の写し等の範囲である。
なお、住民票から除かれた者は住民票の除票の写しを請求できる。
住民票の写し等の第三者請求
住民基本台帳法12条の3第1項は、住民票の写し等の第三者請求について規定している。
住民票の写し等の第三者請求における「第三者」とは次の場合に該当する者である。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
- 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
住民票の写し等の第三者請求はこのような場合に請求できるが、3の場合は1及び2の場合より抽象的・概括的に表現されている。しかし、3の存在によって1、2以外の場合が広く認められるという趣旨ではない。すなわち、3の「正当な理由」は、1、2に準ずるものでなければならない。そして、第三者がこれらのいずれかに該当する場合には住民票の写し等の請求書に該当する事由を記入する。
なお、この3つの事由は司法書士の職務上請求書1号様式の「利用目的の種別」の2欄の「依頼者について該当する事由」と同じである。
また、住民票の写し等の第三者請求においては、請求する住民票の写し等の範囲について住民票の写し等の本人等請求のような制限はない。すなわち、住民票の写し等の第三者請求の対象は請求者本人及びこれと同一の世帯に属する者の住民票の写し等に限られない。
以上が住民票の写し等の請求である。また、本人等請求及び第三者請求いずれの場合でも、委任状を添付すれば任意代理人も住民票の写し等ができる(住民基本台帳法12条4項、12条の3第6項)。つまり、司法書士はこの委任状を添付して本人等請求又は第三者請求をすることで職務上請求で取得可能な住民票の写し等と同じ範囲の住民票の写し等を取得できる。
戸籍の附票の写しの請求
住民基本台帳法20条は、戸籍の附票の写しの請求について規定している。
住民基本台帳法20条は、戸籍謄本等の請求及び住民票の写し等の請求の場合と同様の規定である。よって、これらと同様の取扱いと理解すればよい。
司法書士の職務上請求
戸籍謄本等や住民票の写し等の取得は本人等請求が原則である。しかし、本人等請求は取得できる範囲が限定されているため、本人等請求だけでは手続きに必要な書類が揃わないことが多い。そこで、戸籍謄本等や住民票の写し等が必要な理由を疎明して第三者請求をすることで補完的に必要書類を取得することができる。もっとも、一般の人が第三者請求を使いこなすことは困難である。
そこで、第三者請求の補完として認められたのが職務上請求である。職務上請求により司法書士は戸籍謄本等や住民票の写し等を必要な限度で取得できる。もっとも、前述のとおり職務上請求を使用しなくても、依頼者からの委任状を添付すれば本人等請求及び第三者請求により必要書類の取得は可能である。
また、職務上請求は第三者請求の延長線上に認められる制度であるから、職務上請求をするには前提として第三者請求の要件が具備されていることが必要である。
職務上請求は依頼された業務内容により1号様式と2号様式に区別される。
1号様式
1号様式は司法書士法3条1項や不動産登記規則247条2項2号に規定される業務、すなわち司法書士の資格に基づいて認められる業務を遂行する上で必要な場合に使用する様式である。
2号様式
2号様式は当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人等又は後見人等その他これらに類する地位に就き、委嘱された業務を遂行する上で必要な場合に使用する様式である(基本通達Ⅰ5(1)ウ(カ))。
この業務は司法書士規則31条規定の業務と同じである。
業務の例として、相続財産清算人(管理人)や成年後見人の業務がある。もっとも、このような業務においては請求者たる司法書士に法定代理権があることが一般的である。そのため、職務上請求をせずとも委任状の添付なく必要書類を取得できる。このようにこの場合には2号様式を使用する実益はあまりない。
2号様式を使用する実益としては、2号様式を使用することで司法書士が職務上請求していることが明らかになり、不正請求の抑止に繋がることが挙げられる。例えば、司法書士が法定代理人として市区町村所定の様式で戸籍謄本等を請求する場合、必ずしも司法書士の職名が記載されるわけではない。これに対し、2号様式を使用すれば司法書士の職名が記載される。
また、いわゆる遺産承継業務のために相続関係を証明する戸籍謄本を請求する場合も2号様式を用いる。もっとも、遺産承継業務に不動産登記申請や法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出の代理業務が含まれている場合には1号様式を用いて戸籍謄本を請求する方が直裁的だろう。
戸籍謄本等の職務上請求
戸籍謄本等の職務上請求の規定は戸籍法10条の2第3項、4項である。ここでは同条3項、4項の請求について具体的に解説する。
戸籍法10条の2第3項、4項の請求とは、司法書士の資格に基づいて認められる業務を遂行する上で必要な場合の請求である。よって1号様式を用いて行う。
3項請求
まず、同条3項は「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」に司法書士等が戸籍謄本等を請求できる旨規定している。そして、「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」については通達で具体的に特定されている。すなわち、「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」とは、司法書士が特定の依頼者からその資格に基づいて処理すべき事件又は事務の委任を受けて、当該事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合を指す(基本通達第1ー4ー(1)法務省民一第1000号平成20年4月7日)。
「受任している事件又は事務に関する業務」とは例えば登記申請手続代理業務や裁判書類作成業務である。
また、この通達によれば同条3項の請求においては「特定の依頼者」の存在が必要である。よって、依頼を受任していない時点で職務上請求はできない。
さらに、この通達によれば同条3項の請求は「資格に基づいて」処理すべき事件又は事務に関するものでなければならない。よって、司法書士法規定の業務以外の事件又は事務の依頼で職務上請求はできない。例えば、遺言作成や相続人調査目的で職務上請求はできない。ただし、法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出の代理業務に基づいて職務上請求はできる(不動産登記規則247条2項2号)。
なお、同条3項の請求は職務上請求書1号様式の「利用目的の種別」欄の「2 上記1以外の場合で受任事件又は事務に関する業務を遂行するために必要な場合」に該当する。
4項請求
次に、同条4項は「受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合」に司法書士等が戸籍謄本等を請求できる旨規定している。
- 司法書士法第3条第1項第3号及び第6号から第8号までに規定する代理業務(同項第7号及び第8号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第6号に規定する代理業務を除く。)
そして、「業務を遂行するために必要がある場合」については通達で具体的に特定されている。すなわち、「業務を遂行するために必要がある場合」とは、司法書士が現に紛争処理手続における代理業務を行っている場合のほか、紛争処理手続の対象となり得る紛争について準備・調査を行っている場合も含まれる(基本通達第1ー4ー(2)法務省民一第1000号平成20年4月7日)。
「受任している事件について次に掲げる業務」とは例えば審査請求の代理や簡裁訴訟代理等関係業務である。
また、この通達によれば訴訟の準備段階でも同条4項の請求ができる。
さらに、この通達によれば任意の和解交渉を行うために同条4項の請求ができる。
もっとも、同条4項は司法書士法人が司法書士法第3条1項6号に規定する代理業務を理由に職務上請求できない旨を規定している。なぜ司法書士法人がかかる請求をすることができないかというと、司法書士法人は司法書士法第3条1項6号に掲げる事務については、その社員又は使用人たる認定司法書士に行わせなければならない(司法書士法30条1項)からである。よって、この場合にはかかる事務を行う認定司法書士が同条4項の請求をすることになる。
なお、同条4項の請求は職務上請求書1号様式の「利用目的の種別」欄の「1 司法書士法第3条第1項第3号、第6号から第8号に規定する代理業務に必要な場合」に該当する。
住民票の写し等の職務上請求
住民票の写し等の職務上請求の規定は住民基本台帳法12条の3第2項である。ここでは同条2項の請求について具体的に解説する。
住民基本台帳法12条の3第2項の請求とは、司法書士の資格に基づいて認められる業務を遂行する上で必要な場合の請求である。よって1号様式を用いて行う。
同条2項は、受任している事件又は事務の依頼者が同条1項各号に掲げる者に該当する場合に司法書士等が住民票の写し等を請求できる旨規定している。そして、同条1項各号に掲げる者とは次の者である。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
- 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
つまり、司法書士等が、住民票の写し等の第三者請求における第三者にあたる者から事件や事務を受任していれば同条2項の請求が認められる。
戸籍の附票の写しの職務上請求
戸籍の附票の写しの職務上請求の規定は住民基本台帳法20条4項、5項である。
住民基本台帳法20条4項、5項の請求とは、司法書士の資格に基づいて認められる業務を遂行する上で必要な場合の請求である。よって1号様式を用いて行う。
住民基本台帳法20条4項、5項は、住民基本台帳法12条の3第2項の請求(住民票の写し等の職務上請求)と同様の規定である。よって、住民票の写し等の職務上請求と同様の取扱いと理解すればよい。
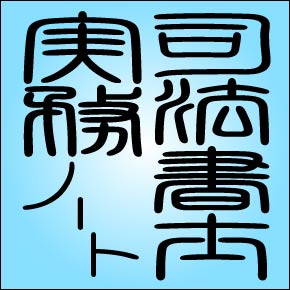 司法書士実務ノート
司法書士実務ノート
先生の話はとても参考になりました。 しかし、中には酷い人もいます。 相続で
1.被代襲者と代襲者を同時に業務上戸籍請求(被代襲者は請求者に全員??)
役所からの第三者に戸籍を取られた報告で判明した。 遺産は1億程度あり
2.受任の範囲、報酬も全く教えてもらえなかった。 包括的相続受託と費用はやらなければ分からいとの事 この方法で30年以上してきたけど問題無かったとの事
3.相続放棄する事と贈与で110万貰う事で親族間では納得したのだが、放棄して裁判所から通知書が送られてきたけど、証明書じゃないとダメだ言い、最後は内容証明を送り付けられた・・結果親族関係が破綻、多くの費用、時間をかけて放棄したのにその対応は流石に怒るだろ。
こちらは初めから争う意思は見せず円満解決を目指していたのに非常に残念でした、当然、受託契約はしていませんけど,真面目に業務している先生が多数だと思いたいですけど、こんな事実だと、司法書士に頼む位なら高いけど弁護士の栓背に頼むかになります。