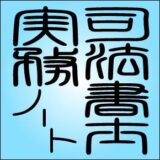目次
オンライン申請とは
登記申請において、申請書という書面を提出するのではなく、申請情報という電子情報提出することをオンライン申請という。
もっとも、通常登記申請情報の添付情報は電子化されていないので、添付情報は紙媒体で提出する。
このように申請情報のみをオンライン申請し、添付書類を法務局に持参(又は郵送)する方法を特例方式という。
特例方式は厳密にいえばオンライン申請ではないが、実務では特例方式のことを書面申請と対比してオンライン申請と呼ぶことが多い。
事務所の方針
過去には特例方式で減税措置が取られていた時期があったが、現在ではそのような差別はない。よって、いずれを選択しても依頼者に影響はない。
書面申請と特例方式のいずれを選択するかは事務所の経営方針に委ねられる。
特例方式の特徴
登記原因証明情報のPDF添付
特例方式では登記原因証明情報をPDF化し、申請情報に添付する。
これは登記原因の実態がないにもかかわらず、登記申請をして受付番号だけ取りに行くという行為、いわゆるカラ申請を防止するためである。
オンライン申請画面
次の行為はオンライン申請画面で行う。
- 「受付のお知らせ」の受領
- 登記完了の確認
- 登記申請の補正・取り下げ
「受付のお知らせ」とは書面申請の登記受領証に相当するものである。
添付書類の提出
特例方式では添付書類は申請日から2開庁日以内に管轄法務局に提出する。つまり、特例方式では登記申請日に法務局申請窓口に赴かなくてもよい。
管轄法務局が遠方であれば特例方式を使うのが一般的だろう。
登記識別情報の提供
特例方式では登記識別情報の英数字を専用フォーマットに打ち込み、申請情報と一緒に送信する。
そして、入力した英数字に間違いがあれば補正通知がくるので、再度入力して送信する。
これに対し、書面申請では登記識別情報通知をコピーしたうえで封筒に入れて提出する。
登記識別情報が発行された当初は特例方式では英数字を入力するのが手間であった。しかし、今では登記識別情報の英数字の横にはQRコードがついている。
そして、これをQRコードリーダーで読み取れば英数字を入力する手間が省ける。
登録免許税の納付
特例方式では登録免許税の電子納付が可能である。
ところで、特例方式で申請しても登録免許税を収入印紙で納付することがあった。なぜなら、電子納付は登録免許税の還付手続きが煩雑であったからだ。
すなわち、以前は申請の取下げによる登録免許税の還付請求を司法書士が代理する場合、登記申請の委任者から司法書士への「登録免許税の還付請求手続きを司法書士に委任する」旨の委任状を提出しなければならなかった。
これに対し、収入印紙で登録免許税を納付すると、申請を取下げた際には再使用証明を申請することができるところ、この手続きでは還付請求のような委任状が不要である。
このような理由から電子納付は避けられていたが、先例変更により登記の委任状に、「登録免許税の還付請求手続きを申請人代理人に委任する」旨の記載があれば、前述の委任状の提出が不要となった。
また、登録免許税の超過納付の場合で1,000円以下の既納付額を放棄する場合は、オンライン申請情報の補正情報に「超過分を放棄する」旨を記載すれば窓口で放棄申請書を提出する必要はないと考えられる。
特例方式と書面申請
他の司法書士と連件申請
他の司法書士と連件申請する場合には書面申請の方が楽な場合がある。
なお、特例方式では次のように他の司法書士と連件申請をすることができる。
※司法書士甲が1件目で所有権移転登記を、司法書士乙が2件目で抵当権設定登記を申請をする場合
受領証の提出
金融機関等に登記申請書の受領証を提出する場合には特例方式が便利である。
書面申請の場合は法務局申請窓口に登記申請書と添付書類を持参し、その上で受領証を発行してもらい、事務所にもどって受領証をFAXする。
これに対し、特例申請の場合はオンライン申請画面で「受付のお知らせ」を受け取ることができる。すなわち、登記申請さえすれば、法務局申請窓口に赴くまでもなく「受付のお知らせ」を受け取ることができる。この「受付のお知らせ」は受領証に代わるものである。
よって、特例方式では法務局申請窓口で受領証の発行を待つ時間がなくなり、受領証FAXのために事務所にもどる手間もなくなる。
さらに、特例方式では登録免許税を電子納付すれば法務局申請窓口ですることは添付書類を提出することだけある。
このように特例方式は外回りの時間を大幅に短縮できる。
登記完了の確認
特例方式の場合は登記が完了したことをオンライン申請画面で確認できる。そのため、登記完了後の登記事項証明書をタイムラグなく取得できる。
すなわち、書面申請の場合、法務局の申請窓口で登記の完了書類を受け取ってから登記事項証明書を取得する。
これに対し、特例方式では法務局申請窓口で完了書類を受けとると同時に、法務局証明発行窓口で登記事項証明を受け取ることができる。
登記完了証
特例方式の場合には登記完了証に登記申請内容が記載される。
これに対し、書面申請の場合には記載されない。
例えば所有権登記名義人住所変更登記や抵当権抹消登記を受託した場合に登記完了後の成果物としては特例方式の登記完了証が優れている。
システム障害
特例方式最大の欠点は法務省のシステム障害時に申請ができないことである。システム障害は申請者で対処しようがない。
これに関しては業務ソフトを導入して、システム障害時に特例方式から書面申請へと切り替えることを推奨する(管轄法務局が近距離の場合)。
申請の難易度
初心者には書面申請の方が楽である。また、法務省の申請用ソフトは使いにくい。
そのため、特例方式を使いこなすには業務ソフトの利用が必須であろう。
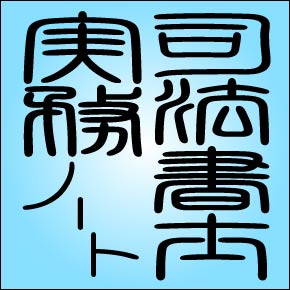 司法書士実務ノート
司法書士実務ノート