共同根抵当権の性質
根抵当権は当事者の意思表示のみで成立する(民法176条)。
しかし、根抵当権を設定する不動産を共同担保の関係にするにはその旨の登記が必要である。すなわち共同根抵当権は登記が効力要件となっている(民法398条の16)。
なお、根抵当権設定契約証書のひな形によってはそれに「共同担保として」の文言を追記することがある。これは共同担保である旨を明らかにするためである。
(共同根抵当)
第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
そのため、複数の管轄にまたがる不動産に共同根抵当権を設定する流れは次のようになる。※管轄が2か所の場合
- 複数の管轄にまたがる不動産につき共同根抵当権設定契約をする
- 一方の管轄法務局へ(共同)根抵当権設定登記を申請する。
- 2の登記完了後、その登記事項証明書(又は照会番号)取得する。
- 他方の管轄法務局へ共同根抵当権設定(追加)登記を申請する。ここで3の登記事項証明書(又は照会番号)を添付する。
設定日と受付日
ところで、複数の管轄にまたがる不動産に共同根抵当権を設定する場合、そうでない不動産に共同根抵当権を設定する場合と同様に根抵当権設定契約日と、その登記申請の受付日を同一にすることが求められる。
しかし、上記の流れにおいては2件目の登記申請の添付書類として、1件目の登記申請完了後の登記事項証明書(又は登記情報)を添付することは物理的に難しい。
そこで、2件目の管轄法務局に事情を伝えて2件目の登記の審査を待ってもらう必要がある。その際には1件目の登記申請の受領証を2件目の添付書類にするなどの配慮がいるだろう。
もっとも、これには条件がある。それは登記原因証明情報たる根抵当権設定契約証書を管轄分用意することである。
複数管轄法務局に添付書類を提出するにもかかわらず根抵当権設定契約証書が1通しかないと添付書類の不備となる。
例
- A法務局管轄の不動産aとB法務局管轄の不動産bに共同根抵当権を設定する
- aとbの根抵当権設定日は同日
- aとbの共同根抵当権設定契約証書が1通ある
根抵当権者はaとbに共同根抵当権の設定契約と登記受付日を同一にしたい。
そこで、各々の管轄法務局にて共同根抵当権設定の登記申請を同日付で受付けてもらう必要がある。
A法務局とB法務局に同日付で不動産登記を申請するならば、登記原因証明情報である根抵当権設定契約証書が2通必要である。
なぜなら、例えばオンライン申請の場合は登記申請日から2開庁日以内に法務局へ根抵当権設定契約証書の原本を提出するからである。
よって、根抵当権設定契約証書が1通しかなければ根抵当権者の要望に応えられないだろう。
なお、B法務局に根抵当権設定契約証書が1通しかないこと説明したうえで登記審査を待ってもらうという案はある。しかし、これは上述の登記事項証明書(又は照会番号)の事情と異なり登記申請者で対応できる事情であるから難しいだろう。
共同抵当権設定の場合
これに対し共同抵当権の場合はこのような問題は発生しない。なぜなら共同抵当権は設定契約のみで成立するからである。
なお、共同抵当権設定の申請書には「管轄外の不動産」を記載をするが、これは共同抵当権が設定契約のみで成立し、登記は対抗要件であることを意味する。
もっとも、共同抵当権の場合にも登録免許税13条2項の適用を受けるために前述の同様に登記事項証明書(又は照会番号)を添付する。
そのため、共同抵当権の場合も事実上共同根抵当権と同様の手はずとなる。
共同根抵当権設定の申請書
共同根抵当権設定(1件目)
登記の目的 共同根抵当権設定
原 因 令和年月日設定
登録免許税 極度額×0.4%(原則)
なお、この申請書には管轄外の物件は記載しない。
共同根抵当権設定(追加)(2件目)
登記の目的 共同根抵当権設定(追加)
原 因 令和年月日設定
登録免許税 不動産の数×1,500円(登録免許税法13条2項)
前登記の表示
前登記不動産の所在・地番(又は所在・家屋番号)
前登記の根抵当権の順位番号
なお、登記の原因の日付は根抵当権設定契約日であり、2件目の登記申請日ではない。
また、前登記証明書として1件目の登記完了後の登記事項証明書か照会番号を提出する。
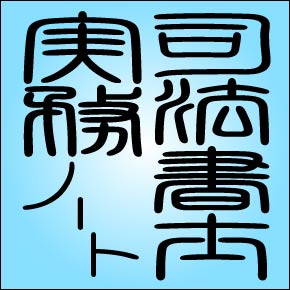 司法書士実務ノート
司法書士実務ノート